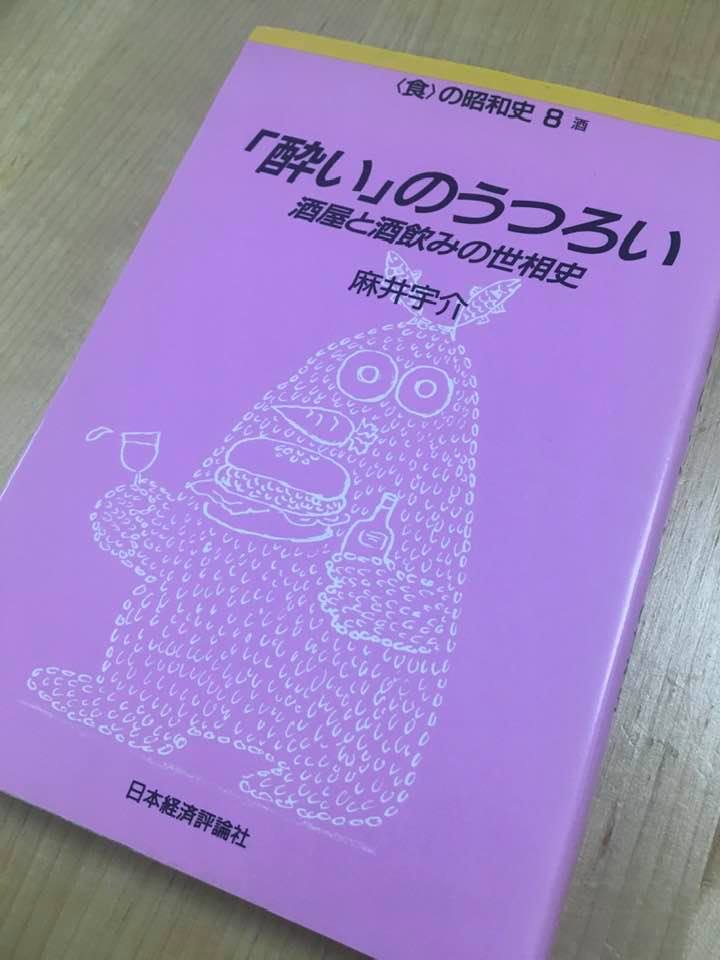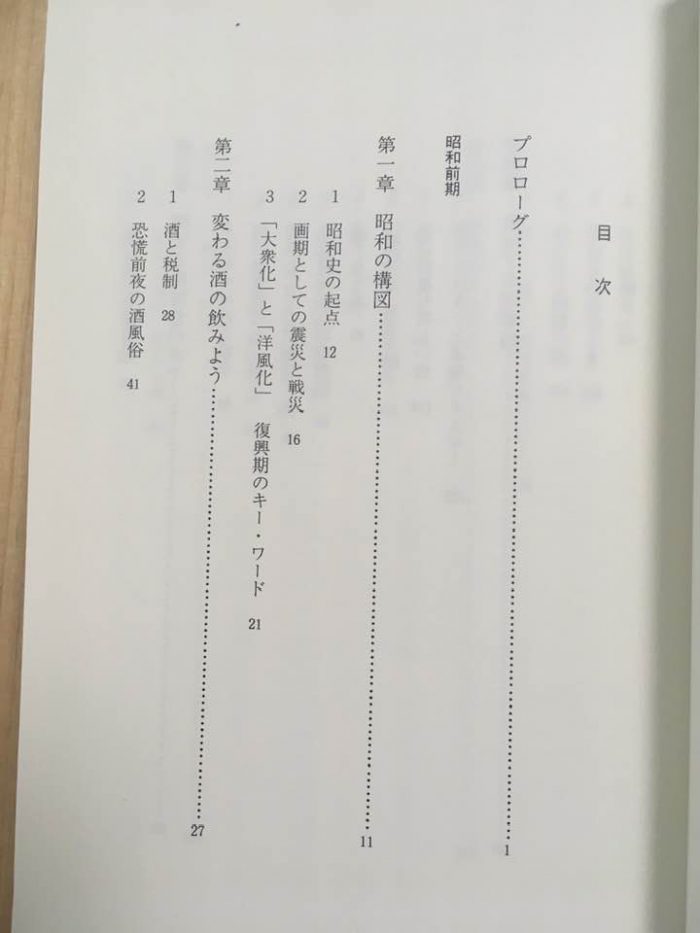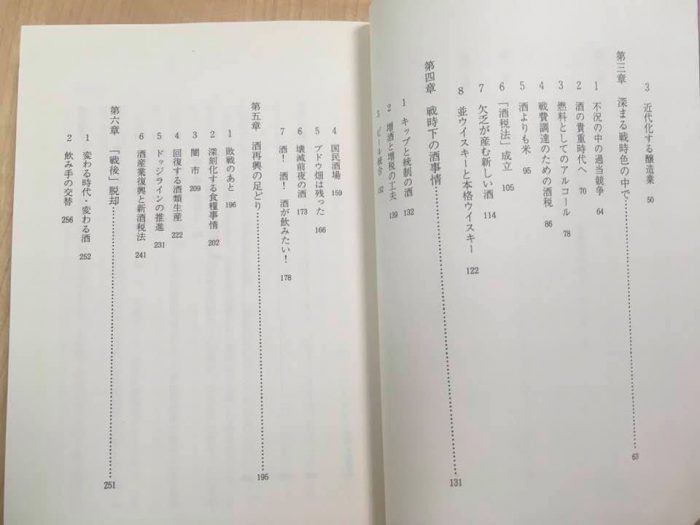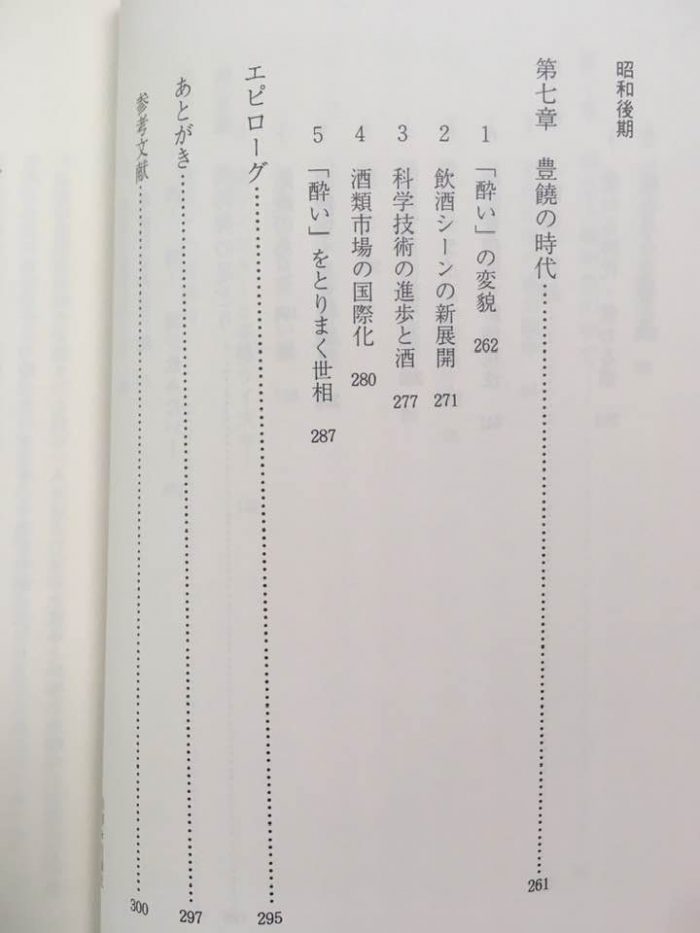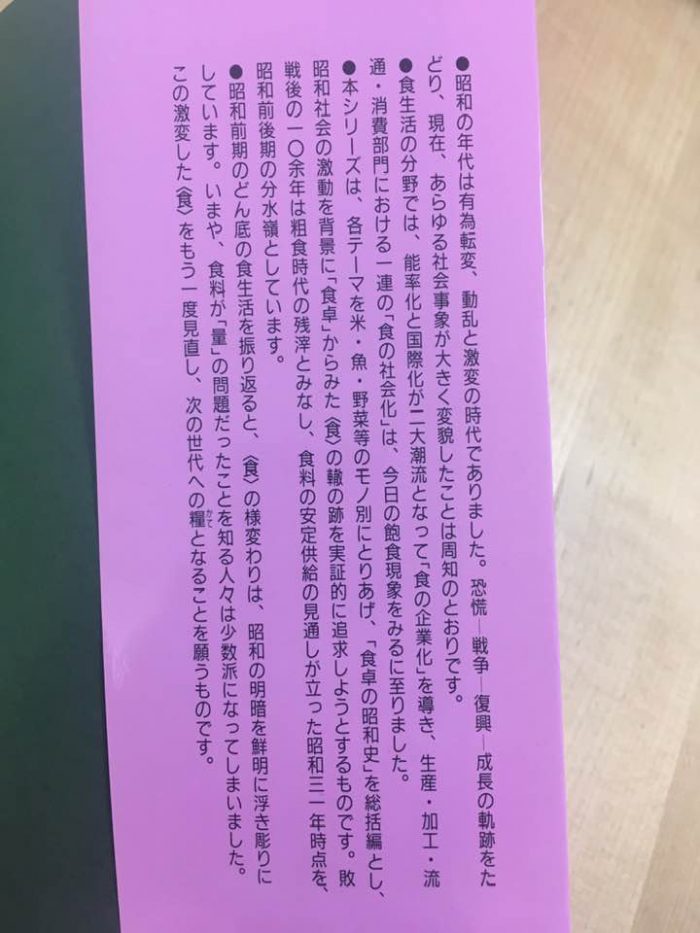「7日間ブックカバーチャレンジ」5日目
『「酔い」のうつろい 酒屋と酒飲みの世相史』麻井宇介
1988年に世に出された一冊。「麻井宇介」といえば「ウスケボーイズ」といえば「教科書を捨てなさい」みたいなことになっていますが、僕は、人間の歴史を俯瞰する視点にこそ、麻井さんの稀有な凄さがあると感じています。なぜ酒を飲むのか、飲みたいのか、どう飲まれてきたのか、酒を前にした人間は…。
「ありあまる情報に彩られた過去は、少し遠くなってからでないと歴史は見えてこない。記憶の濃密さが歴史を見る眼を曇らせるからではない。有為転変の中にも、緩慢にしか進まない歴史があるからである。」
「時代の曲がり角であった1960年代の始まる頃、戦中・戦後を象徴する酒、焼酎と合成清酒がピークに達した。この頃をもって、「酔い」に対する人々の灼けるような渇きはいやされたとみてよい。酒類全体の消費が伸び続ける中で、これ以後、飲み手の欲望は「酔い」そのものを求めることから、「何を飲みたいか」に関心が移っていく。」
「地酒復権は平明さの対極にある「知る」ことの楽しさから興っている。このことは、「知的生活」への人々の心が動き始めていた当時の風潮とも合致していた。「分衆」「個衆」といった言葉が生まれ、大衆消費社会の終焉が論じられる時代となって、酒もまた情報の濃さが商品の強さとなりだしたのである。」
「地酒とは、その土地にして初めて生まれる固有性をもつものである。必然的に地酒は多種多様を誇る。ここに、生理的な「酔い」を離れて、なお陶酔に誘うものがあるからこそ大衆化のなかで埋没をまぬがれてきたのであった。その典型は、銘醸地のワインである。」
「ワイン消費がなかなか一般化しなかった理由を考えれば、すでに定説化している「日本人の食生活とあわなかった」ことよりも、「日本人の飲みようとあわなかった」ことを第一にあげるべきであろう。かつて、われわれは酒を「酔う」ために飲み、ワインは「酔う」ことを目的としない飲み方、すなわち食中酒として、ラテン系民族の生活の必需品となっていたからである。」
「これから先、日本人はいかなる「酒の飲みよう」を好み、いかなる「酔いのありよう」を求めるのであろう。輸入酒であれ国産酒であれ区別はない。それに応える酒しか生き残れない時代へ、どうやらさしかかったようである。」
ライフスタイルや習慣、価値観や飲み方に影響が及ぶいまも、もしかしたら転換期かもしれません。これまでと、これからの、酒と人間の付き合い方とは…。
USED本がまだ入手できるようですので是非。